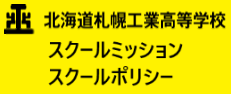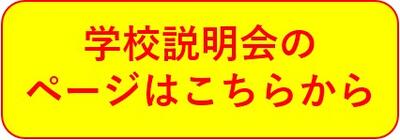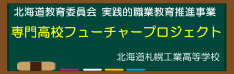2024年7月の記事一覧
2024/07/22(月)~室蘭工業大学にアカデミックインターンシップいきました~「室蘭工業大学・企業との連携」
アカデミックインターンシップで、1~3年生の希望者22名が、室蘭工業大学へ行きました。
前半は三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社の御協力で工場見学を実施しました。地球に優しく高品質な特殊鋼造りついての説明と実際の製造工場を見学させていただきました。
後半は、ロボットアリーナで講義と、もの創造系領域 小室教授、しくみ解明系 山中教授、もの創造系領域 中田准教授から講義や実技指導をいただきました。
生徒達は “3講義をすべて受けることができ、機械だけでなく様々な科の内容を確認することができたので、自身の進路選択の幅が広がって良かったです。また、見学した三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社では、圧延や精整の工程を見学することができ、会社が行っている事業に対する理解度を高めることができたので良かったです。室蘭工業大学も進学の候補に入っているので、講義の内容だったり雰囲気だったりを事前に知れる貴重な時間だったので参加して良かったと思いました。” ”今回は訪れることのできない三菱特殊鋼製造所や室蘭工業大学の訪問など、札幌工業高校でしかないような機会なので入学して良かったと思いました。工場見学では棒鋼の製造過程について見学しました。かなりの規模なため、車で移動しているのに驚きました。工場内で働いている方々は暑い中の作業でかなり大変だと思いますが、お客様のことを一番に考えており、さすが職人と感じました。室蘭工業大学の見学では模擬講義を実施していただき、普段の大学の授業を感じることができました。室蘭工業大学で目指している生徒の姿、教育課程など調べるだけではわからないようなことも知ることができました。今回の体験を胸に刻みながら今後の進路について考えていきたいです。” ”オープンキャンパスでは見られなかった部分の見学をさせていただき、室蘭工業大学についてさらに知ることが出来ました。” ”気になっていた大学について知るためという理由で参加したので、知識がありませんでした。しかし、大学の研究について詳しく教えてもらうことによって、自分で研究して設計したり制作したりしてみたいと思いました。さらに、大学院で好きなだけ研究したりと室蘭工業大学でできることを多く知れたと思います。今回説明してもらったことを今後の進路に活かせて行けるようにしたいです。” と話していました。
2024/07/19(金)~サクラマスの産卵床作りました~「企業等とのコラボレーションチャレンジ」
札幌工業高校土木科では、毎年、琴似発寒川の環境と治水を大きなテーマとして、「課題研究」に取り組んでいます。今年度は「サクラマスの産卵場所を増やす」ことを1つの課題に設定しました。
都市河川の琴似発寒川は、護岸や床止めなど、人の暮らしの安全のため、さまざまな整備が行われました。その結果、ところによっては川底の砂利が流されたあと、上流から供給されず、サクラマスの産卵適地は限られています。そこで、サクラマスの生態、河川環境、治水等を探究し、「自分たちでサクラマスのための産卵場所を作る」ことになりました。
7月19日、生徒達は、砂利を溜まっているところから運び出し、砂利がなくなって岩盤が出てしまっているところに運び込み、産卵床を作りました。当日は、琴似発寒川の管理者である空知総合振興局札幌建設管理部、札幌市豊平川さけ科学館、北海道技術コンサルタントの方々に御協力をいただきました。
また、NHKの取材も入っており、10月位に放映の予定です。あとは、サクラマスが来て、産卵してくれることを願います。今後は期間をおいて、今回実施内容の検証を進めます。
2024/07/17(水)~環境学習に行きました~「企業とのコラボレーションチャレンジ」
1年土木科の生徒が琴似発寒川において、土木工事と環境保全について学習しました。
近年、異常気象など平年から大きくかけ離れた天候により社会的に大きな影響をもたらしており、札幌市も例外ではありません。土木工事の中でも河川工事は生態系、環境に与える影響が大きいため、工事の際は環境保全に配慮しなければなりません。
北海道技術コンサルタント様の技術士の方や本校卒業生、札幌市豊平川さけ科学館の御協力を得て、生態系や河畔林についてご指導をいただき、生徒達は環境保全の大切さと土木工事との関わりについて深く探求することができました。
生徒達は “生態系を考えて土木工事を進めなければならないことを知った。” “生態系や河川に関わる工事について、専門的な知識を学ぶことができました。” “実際の工事や設計、計画について、専門的な授業をうけることができた。” ”人々の安全を守りながら、元々いた生物にも配慮しなければならないことを知りました。“と話していました。
2024/07/10(水)~現場見学会に参加しました~先端技術講義「札幌建設業協会・企業との連携」
2年土木科の生徒が札幌建設業協会様の御協力で現場見学会に参加しました。
玉川組様の御協力で、令和5年度 障害防止対策事業 漁川第二頭首工4期工事(恵庭市)、新太平洋建設様の御協力で、白川第4浄水棟場内連絡管新設工事その1(南区白川)の見学を行いました。
GNSS、トータルステーション、ドローン、情報化施工、VR、ARと最新の土木技術を見学・体験することができました。また、本校卒業生の技術者より講話もいただきました。
生徒達は“頭首工について理解することができた。” ”ICTがこれほど使われているとは思わなかった。” “各現場で札工の先輩技術者から、建設業界にかかわり、色々な生の話を聞くことが出来て、就職活動への不安が少し解消しました” ”建設業で働きたくなった。” と話していました。
2024/07/09(火)~9th GEWEX-OSC 2024 SAPPORO(第9回全球エネルギー水循環プロジェクト国際会議)に参加しました。~
3年土木科の環境にかかわる課題研究に取り組んでいる生徒が9th GEWEX-OSC 2024 SAPPORO(第9回全球エネルギー水循環プロジェクト国際会議)に参加しました。
今回の会議の趣旨は、地球温暖化問題に対する緩和策と適応策の立案及びそれに向けた気候変動の将来予測は、今、全世界で取り組まなければならない喫緊の課題です。本国際会議は当該分野で国際的に活躍する世界各国からの関係者が集結し、全球スケール及び地域スケールのエネルギー循環や水の挙動に関する最新の研究成果や取り組みを共有し、議論する場となります。
我が国の水循環科学や気候変動に関する研究は世界を先導する水準にあります。これらの研究で確立された地球観測や数値シミュレーション等の先進技術と、研究によって得られた科学的な知見は、地球温暖化対策のための基盤情報・技術として未来の日本の社会づくりに貢献しており、これらの一連の活動は国連気候変動枠組定例会合(UNFCCC)で報告されました。
本会議では、日本が先駆的に進めてきた最新の研究と社会での応用事例を北海道・札幌から世界に向けて発信し、これらの分野における日本の位置づけをさらに躍進させるとともに、分野や地域の垣根を超えた高度な連携の機運を高め、道民を始めとする国民全体の気候変動や防災への意識醸成につなげたいと考えている会議となります。
札幌工業高校では、ヒートパイプを用いたエネルギー循環等や、琴似発寒川で継続している、治水や河川環境についてのパネル展示を行いました。多くの質問や意見をいただきありがとうございました。
参加した生徒は ”国際会議に参加できて良かった。” ”世界各国の方々と交流を深めることができた。” ”地球温暖化について理解が深まった。” ”気候変動にかかわる防災対策について考えていきたい。” と話していました。
2024/07/03(水)~管路更生システム「SPR工法」出前講義いただきました。~先端技術講義「企業との連携」
土木科2年生が、積水化学北海道株式会社様・一二三北路株式会社様のご協力で管路更生システム「SPR工法」出前授業を受講しました。今回講義を受けた管路更正方法は、老朽化した下水管等を道路等を掘り返さず、既設管の内側に硬質塩化ビニル製プロファイルの更生管を製管し、既設管と更生管の間隙に特殊裏込め材を充填し、古くなった管きょを既設管・更生管 ・裏込め材が一体となった強固な複合管として蘇らせる工法です。
最初に管路更正方法ついて本校の卒業生より講義をいただきました。技術説明の他に進路についての講話もいただきました。その後は、本校駐車場にて実演を行い、技術指導をいただきました。
生徒達は、“管路更生工法について詳しく理解できた。” ”掘削しないので工期が短縮できる。” “廃棄物も少ないのでSDGsで地球に優しい” “建設業について、色々な話を聞いたり、質問も出来て、来年の就職活動に向けてとても参考になりました。” と話していました。