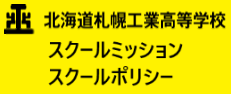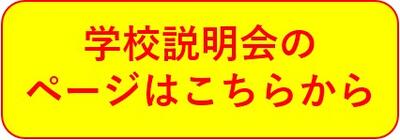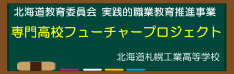地域・企業・大学・他校種・各機関等との連携による活動
2024/5/13(月)~先輩から講話をいただきました~ 「企業との連携による活動」
令和6年度卒業生講話を土木科1年生を対象に、伊藤組土建(株) 佐野様、札建工業(株)高橋様、杉原建設(株)村井様、北土建設(株)古山様、丸彦渡辺建設(株)片桐様を講師にお招きして実施しました。
講師の皆様より、現場の実体験や最新技術など実践的な内容や、高校生活の有意義な過ごし方を含めて講義をいただき、学習意欲の向上はもちろんのこと、地域産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力の育成を図ることができました。
生徒達は “先輩からの話を聞いて、建設業について、理解することができました。” ”建設業に就職したいと思いました。” “卒業後の目標を決める貴重な機会となりました。” “建設業へのイメージが変わりました。” と話していました。
2024/5/2(木)~今年も「もっちー広場活用プロジェクト」始動しました~ 「地域・日本技術士会・企業との連携による活動」
「もっちー広場活用プロジェクト」が今年度も始動しました。
3年土木科生徒16名が公益社団法人 日本技術士会北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会の技術士の方から、これまでのプロジェクトの流れや、子どもから高齢者まで多世代の人々が集い、楽しみ、愛着がもてる「みんなの広場」作りのため、全体計画について御指導をいただきました。
生徒達は “今まで土木科で学んだ技術を地域に役立てたい。” “技術士の方に専門的なお話をいただき、大変勉強になりました。” “地域の課題を解決したい。” と話していました。
今年度も、学校、地域住民、企業等が連携し、生徒たちが主体的に学び、その成果を発信する場を充実させ、地域の課題解決や地域創生の実現に向けた取組をすすめ、地域と歩む持続可能な教育の実現を目指します。
2024/4/26(金)~ICT施工でグランド整備しました~ 「企業との連携による活動 先端技術講義・技術指導」
2年土木科が、地崎道路株式会社様から、「ICT施工を用いたグランド整備について」の先端技術講義及び技術指導をいただきました。
本校OBを含む熟練技術者の方々に、ICT施工について、始めに教室で、本日施工するマシンコントロール用の3次元設計データの作成実演や3次元データの利活用方法についての説明や、現場での体験談をいただき、熟練技術者と意見交換を行いました。
その後、グランドにて技術指導(測量~3Dレーザースキャナー・GNSS・トータルステーション、MC~マシンコントロール一式等)や建設機械の体験試乗を行いました。
生徒達は “建設業についての印象がかわりました。” “今日の講義で舗装工事の工程を理解することができました。 ”デジタル技術の活用で、以前より時間を短縮でき、誤差やミスも起きにくく、色々な面で工夫されていて感動しました。” ”丁張りをかけずに、3Dレーザースキャナーやドローンを活用した測量等、多くの最新技術を取り込んで活用していてすごいなと思いました。” ”実演や体験をすることでICT施工について深く理解することが出来ました。” ”将来働いてみたいと思いました。” と話していました。
施工完了後のグランドは、3D図面通りに、きれいに整備され安全・快適に授業や部活動に使用することが出来るようになりました。
2024/03/18(月) 「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! セルフ・ブランディングプログラム~土地家屋調査士会からご講演いただきました~
1年土木科がセルフ・ブランディングプログラムで、「札工生から土地家屋調査士」を演題に札幌土地家屋調査士会 浅野 裕士様から御講演いただきました。
土地家屋調査士や各種資格について理解を深め、工業高校の特色を生かしながら、産業界に貢献できる実践的な知識・技術を身に付けることが出来ました。
生徒達は ”今後の進路の参考になりました“ “土地家屋調査士について詳しく知ることが出来て良かった” “資格を取得することによって、将来どのように役立つかを、実体験をもとに説明いただき、資格取得への、モチベーションが上がった”と話していました。
2月2日(金)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育受講しました。~
土木科1年生が、一般財団法人 北海道建設業協会様のご協力で第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育を受講しました。
第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育とは、酸素欠乏症の危険がある建設業や製造業などで、安全・衛生的に作業をおこない、事故を予防するための知識を身につけるためで、工事現場等での労働災害を発生させないためにとても大切な講習です。
生徒達は “酸素欠乏に係わる知識について、理解を深めることが出来た。” “就職後、酸素欠乏するような場所での安全管理方法を身につけることが出来た。”と話していました。
受講を終了した生徒は、後日修了証が交付される予定です。